4P分析とは、Product(製品)、Price(価格)、Promotion(販促)、Place(流通)の4つのPの頭文字をとったマーケティング戦略を考えるうえでのフレームワークです。
- Product(製品)⇒ 何を売るか?
- Price(価格)⇒ いくらで売るか?
- Promotion(販促)⇒ どうやって認知させるか?買ってもらうか?
- Place(流通)⇒ どこで売るか?
4つのPについて1つ1つ見ていきます。
Product(製品)
どのような商品、サービスを市場に出すかを考えます。
製品については
・どういった人に売るか?
・今のトレンドはなにか?
・製作コストはどれくらいかかるか?
・競合はいるか?
・既存商品(サービス)との違いは?
というようなポイントを押さえて考える必要があると思います。
Price(価格)
次に価格設定について考えます。
価格は利益、売上に直結するだけでなく、製品イメージや市場でどういうポジショニングをとれるかなどに関わってくる重要なポイントです。
価格設定には大きく3つの決め方があります。
- コスト志向
- 競争志向
- 需要志向
コスト志向
もっとも代表的な方法は、原価に一定の利益を上乗せする方法です。
これはコストが明確に把握できて、商品数の多いスーパーマーケットでよく使われます。
競争志向
こちらは競合他社の価格を参考に価格設定をする方法です。
基本的には市場で先行して製品を出している企業に追随する形で価格が決まります。
需要志向
需要志向というのは、顧客が支払っても良いと考える価格から、利益が最大になるように価格を決める方法です。顧客が支払っても良いと考える価格は留保価格とも言います。
Promotion(販促)
どのように商品を知ってもらうか、購入を促せるかを考えます。
実際に商品を購入するまでには注意をひきつけ(Attention)、興味をもってもらい(Interest)、欲しいと思って(Desire)、購入に至ります(Action)。
このAIDAのどの段階に、どういったアプローチをするかを考える必要があります。
例えば商品がまだ多くの人に知られていない状況なら、大衆的に認知してもらえるようテレビCMやチラシを配るなどを考えないといけません。
すでに認知されているような状況の場合、より興味をもってもらい、欲しいと思ってもらえるようなアプローチをしていく必要があります。
訴求内容については以下の3つの観点で分類することができますので参考にしてみてください。
- 情報提供型:認知・理解促進を促す
- 説得型:興味・欲求を喚起し購入まで促す
- リマインダー型:イメージ構築や記憶を呼び起こす
Place(流通)
流通では、商品をどこで販売するのか(販売場所)、どのように商品を届けるのか(配送)を考えます。
チャネル(流通経路)は長さと広さで分けられます。
長さは消費者に販売するまでに、どれくらいの流通業者がはいるのか、メーカー→卸売→小売→消費者と消費者に届くまでに介在する業者の数を考えます。
これは数が多くなればなるほど、それぞれが利益を考え戦略を考えるので、マーケティングとしての管理が難しくなり、全体として得られる利益が最大化できないという危険性もあります。
広さは以下のお3つに分類されます。
- 開放的チャネル
- 独占的チャネル
- 選択的チャネル
まとめ
4P分析はマーケティングを考えるうえでの基本的な観点を示してくれます。
提供する製品やサービスによってはすべて考える必要はないと思いますが、販売戦略を考える上ではこれらの観点を中心に戦略を練ると良いでしょう。
またこれらの戦略において最も重要なのは、顧客のニーズに基づいて考えることになります。
コストや現状の強みだけにとらわれず、活用してみてください。
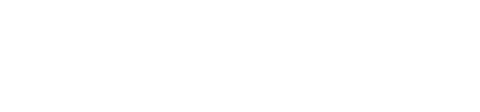



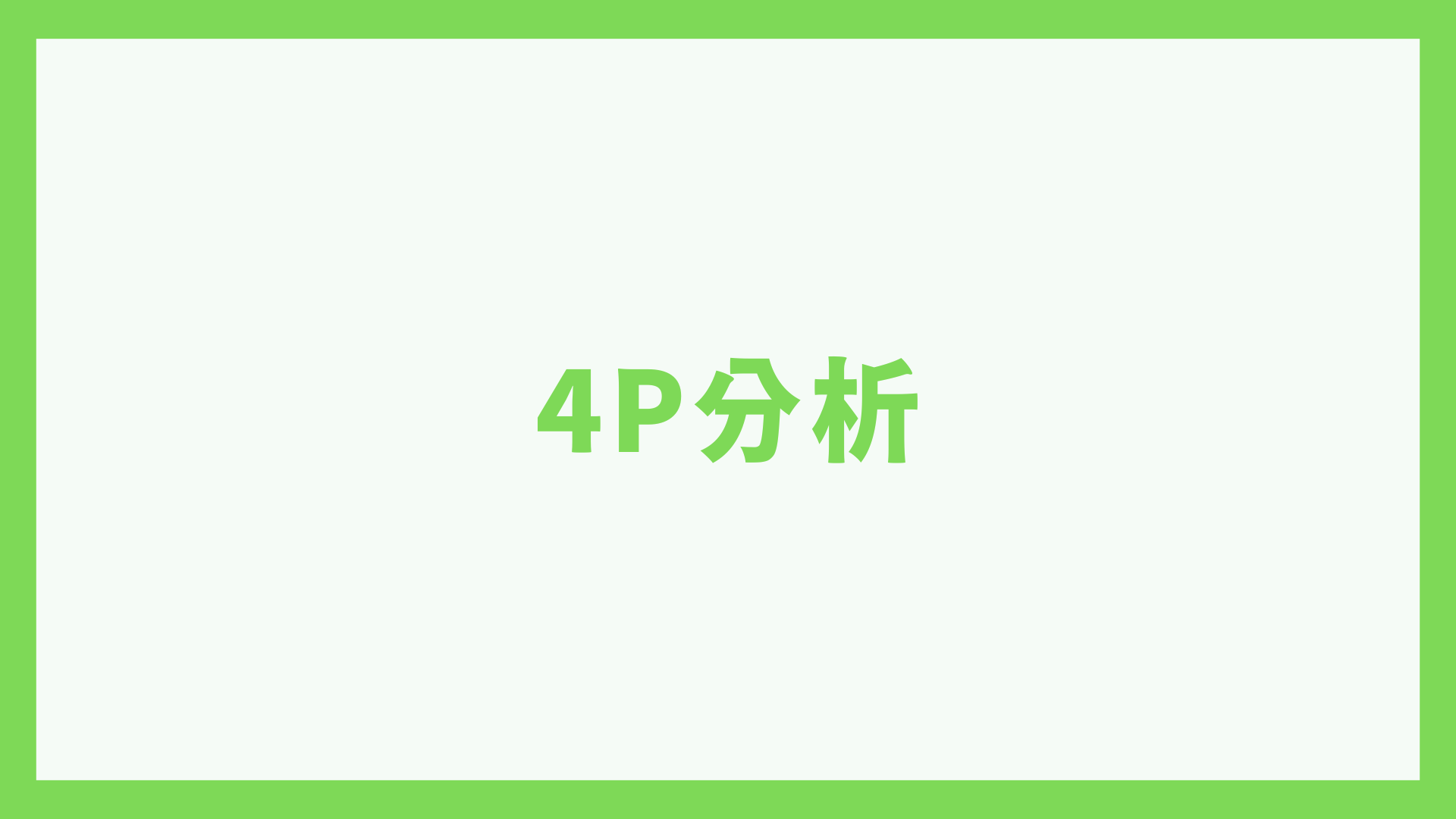

コメント